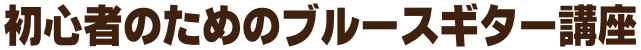コール・アンド・レスポンス
一人で弾語りをする分には気になりませんがバンドスタイルなど他人とセッションをする場合、ブルース事体の構造を理解していないと良い演奏は出来ません。
コール・アンド・レスポンス
ブルースを構成する重要な要素に「コール・アンド・レスポンス(呼び掛けと応答)」があります。
コール・アンド・レスポンスを分かりやすく表現すると
「今朝目が覚めたら、うちの女房がいないんだ~」
「は~それからどした~」
「俺は慌ててあちこち探したよ~」
「は~それからどした~」
「机の上に書き置きがあった~ 若い男と駆け落ちしやがったんだよ~」
「そりゃ大変だ~大変だ~」
民謡風になってしまいましたが(笑)、まあこんな感じです。要するにストーリーに対して合いの手を入れるということです。
一般にブルースは4小節×3行の構造になっていて、ふつう図4_1のように前2小節がコール、後ろ2小節がレスポンスになります。
コール・アンド・レスポンスはもともと、アフリカの民族音楽の歌唱形態(ワーク・ソングなど、リーダーが歌って他の者が追随する形式)から来たものです。
ブルースでは主にコールの部分をボーカル、レスポンスの部分を楽器が担当します。
リードギターのオブリガードは当然レスポンスの部分に入れるわけですが、単純な合いの手で無くボーカルの盛り上がり方をよく聞いて一緒に盛り上がっていくのが理想です。
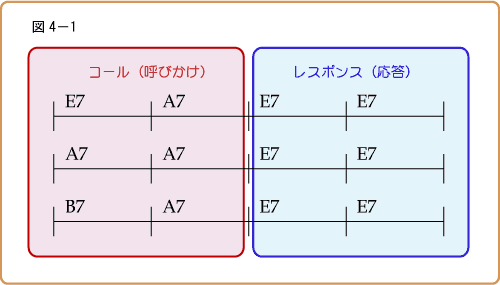
起承転結
曲の間奏などで、ギターソロをとる場合は逆にコールの部分(レスポンスと両方の場合もあり)をギターが担当するわけで、起承転結を考えて曲全体の盛り上がりを引っ張っていかなければなりません。
初心者にも分かりやすい一番単純なアドリブの組み立て方はAAB形式をとる方法でしょう。「起」の部分と「承」の部分を同じメロディーで、「転」の部分で変化を付け「結」でまとめる構成です。
それができるようになったら「承」の部分で「起」のメロディーに少し変化をつけるAA'B形式に挑戦して下さい。
「転結」の部分は非常に重要でここでこけるとカッコがつきません。常套句的なものでかまいませんから得意のフレーズ・パターンをいくつか持っておきましょう。
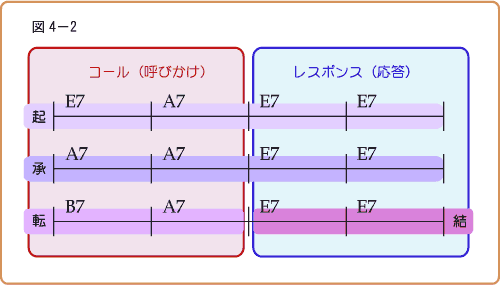
[PR]